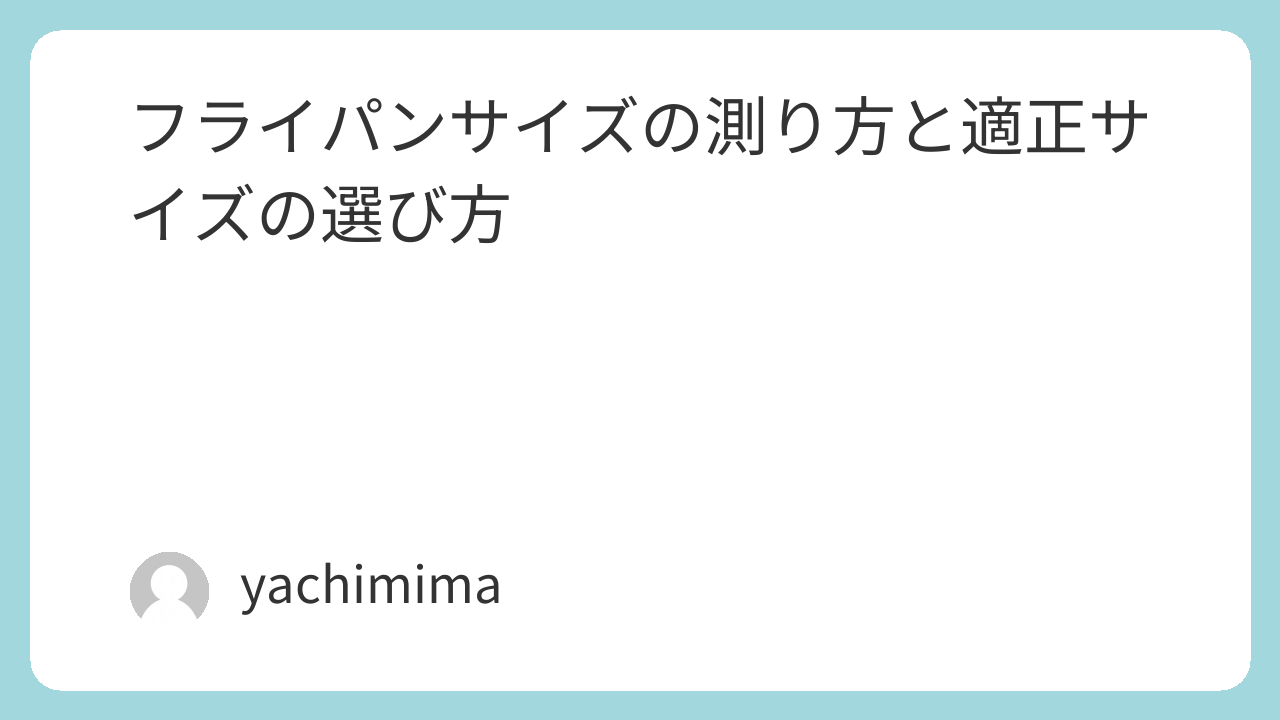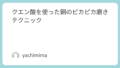「フライパンのサイズ選びって、どうやればいいの?」
そう思ったことはありませんか? フライパンは毎日の料理に欠かせない道具ですが、適切なサイズを選ばないと、使いにくかったり、収納しづらかったりと不便に感じることもあります。「小さすぎて料理がこぼれる」「大きすぎて収納に困る」といった悩みを持つ方も多いのではないでしょうか。
本記事では、フライパンのサイズの測り方、各サイズの特徴、そして用途別の選び方について詳しく解説します。さらに、人気メーカーであるニトリやティファールのサイズ展開についても紹介。これを読めば、自分にピッタリのフライパンサイズがわかるだけでなく、料理がもっと快適に、楽しくなるはずです。失敗しないフライパン選びのポイントを押さえて、あなたに最適な一枚を見つけてみませんか?
フライパンサイズの測り方
フライパンの直径の測定方法
フライパンのサイズは一般的に直径(外径)で表されます。測定する際は、フライパンの縁の外側から反対側の外側までの長さを測ります。多くのメーカーではこの外径を基準にサイズを表記しています。ただし、フライパンの形状によっては測定方法が異なる場合もあります。たとえば、波型やリブ付きのフライパンでは、最も広い部分を測る必要があります。また、底面の直径が表記されることもあり、IHクッキングヒーターで使用する場合は底面サイズを確認するとよいでしょう。
フライパンの深さの測定方法
フライパンの深さは、底面から縁までの高さを測ります。特に炒め物や煮込み料理に使う際は、深さが重要なポイントとなります。深めのフライパンは食材がこぼれにくく、用途の幅が広がります。また、フライパンの角度によっても使い勝手が変わるため、傾斜が緩やかなものは混ぜやすく、急なものは油が飛び散りにくい特徴があります。さらに、底が平らなものは安定性があり、揚げ物にも適しています。
サイズ表記の理解と注意点
メーカーによってサイズ表記の基準が異なる場合があります。特に内径と外径が異なる場合があるため、購入前に確認することが重要です。また、取っ手を含めた長さが商品説明に記載されている場合もあるため、収納スペースを考慮する際には注意しましょう。さらに、一部のメーカーではリットル表記で容量が示されることもあり、スープや煮物を作る際にはこの情報が役立ちます。用途に応じて、サイズ表記の意味をしっかり理解しておくと、より適したフライパンを選ぶことができます。
フライパンサイズ一覧
一般的なフライパンサイズの比較
| サイズ(cm) | 用途例 |
|---|---|
| 18cm | 目玉焼き・一人分の調理 |
| 20cm | 少量の炒め物・オムレツ |
| 24cm | 二人分の調理・パスタ |
| 26cm | 三人以上の調理・炒め物 |
| 28cm | 大人数向けの調理・揚げ物 |
用途別フライパンサイズ一覧
- 小型(18~20cm):一人暮らし向け、小さめの調理に最適。
- 中型(24~26cm):家庭での一般的な調理に適している。
- 大型(28cm以上):大人数の食事作りや揚げ物向き。
ニトリやティファールのサイズ展開
ニトリやティファールなどの人気メーカーでは、20cm、24cm、26cm、28cmのサイズ展開が一般的です。特にティファールはセット販売されていることが多く、用途に応じたサイズ選びがしやすいのが特徴です。また、ティファールの取っ手が取れるシリーズは収納に便利で、フライパンのサイズ違いを組み合わせて使うことで、さまざまな料理に対応できます。
ニトリのフライパンは、コストパフォーマンスが高い点が魅力で、初心者向けから本格調理向けまで幅広いラインナップが用意されています。特に深型フライパンやマーブルコートのフライパンなど、耐久性や焦げ付きにくさに優れた商品も多く、長く使える点がメリットです。
さらに、両メーカーともIH対応モデルが豊富に揃っており、ガスコンロとIHの両方で使えるタイプも販売されています。そのため、自宅のキッチン環境や調理スタイルに合わせて選ぶことが可能です。
フライパンの選び方
料理の種類に応じたサイズ選び
- 卵料理や少量の炒め物:20cm程度
- パスタや野菜炒め:24~26cm
- 焼き魚や大きめの料理:28cm以上
家族の人数に最適なサイズ
- 1~2人:20~24cm
- 3~4人:24~26cm
- 5人以上:28cm以上
一人暮らしに適したフライパン選び
一人暮らしでは、収納スペースや調理のしやすさを考慮し、20~24cmのフライパンが最適です。フタ付きや取っ手が取れるタイプを選ぶと、収納や洗い物の手間が軽減できます。
また、一人暮らしではコンロの口数が限られている場合が多いため、多用途に使えるフライパンを選ぶのがポイントです。例えば、深めのフライパンを選べば、炒め物だけでなく、煮物や簡単な揚げ物にも対応できます。さらに、底面が広いものを選べば、食材を並べやすく、効率よく調理できます。
加えて、素材の選び方も重要です。手軽に扱いたい場合は、軽量で焦げ付きにくいフッ素樹脂コーティングのものが便利です。逆に、料理を楽しみながら本格的に使いたい場合は、鉄製フライパンを選ぶのも一つの方法です。耐久性が高く、高温調理に向いているため、料理の幅が広がります。
さらに、一人暮らしのキッチン環境では、収納スペースが限られていることが多いため、スタッキングしやすい形状や、コンパクトに収納できるアイテムを選ぶのもおすすめです。取っ手が外せるフライパンは、収納時に場所を取らず、洗いやすいという利点もあります。
フライパンの素材とその特徴
フッ素樹脂コーティングの利点
フッ素樹脂コーティングのフライパンは、焦げ付きにくく、少量の油で調理できるため、初心者にも扱いやすいのが特徴です。また、食材がスムーズに滑るため、オムレツやクレープなどの繊細な料理にも向いています。ただし、高温調理には適さず、強火での使用や金属製の調理器具の使用はコーティングを傷める原因になります。また、寿命が比較的短く、コーティングが剥がれると買い替えが必要になるため、耐久性を考慮するなら慎重に選ぶことが大切です。
鉄製フライパンの特徴と手入れ
鉄製フライパンは、耐久性が高く、適切な手入れをすれば長年使用できます。特に高温調理に適しており、ステーキや炒め物を香ばしく仕上げることが可能です。使い込むほどに油が馴染み、自然なノンスティック効果が生まれるのも魅力です。ただし、錆びやすいため、使用後はすぐに洗って水分をしっかり拭き取り、油を薄く塗って保管する必要があります。初回使用時には「焼き入れ」や「油ならし」といった手入れを行うことで、より使いやすくなります。
セラミック・チタン製のフライパンについて
セラミックコーティングのフライパンは、耐熱性が高く、健康に配慮した調理が可能な点が特徴です。焦げ付きにくく、比較的軽量で扱いやすいものが多いですが、長期間使用するとコーティングが摩耗しやすいというデメリットもあります。一方、チタン製フライパンは非常に軽量で耐久性があり、金属ヘラを使用しても傷つきにくいのが特徴です。また、チタンは腐食しにくく、熱伝導性にも優れているため、調理の際にムラなく均一に熱を伝えることができます。ただし、価格がやや高めであるため、コストを考慮して選ぶ必要があります。
フライパンの用途別おすすめサイズ
玉子焼き用フライパンの選び方
四角い形状の卵焼き専用フライパン(約13×18cm)が一般的です。このサイズは卵焼き以外にも、少量の野菜炒めやソーセージの調理にも適しています。また、コンパクトなサイズのため、キッチンの収納スペースを取らず、一人暮らしや小さなキッチンでも使いやすい点がメリットです。素材によっては、熱伝導率が異なるため、焼きムラが気になる場合は、厚みのある鉄製やアルミ製を選ぶと良いでしょう。
揚げ物に適したフライパンのサイズ
深さのある26cm以上のフライパンが適しています。特に、鍋のように深めのデザインのものを選ぶと、油の飛び散りを防ぎやすく、揚げ物がしやすくなります。さらに、温度調整がしやすいタイプのフライパンを選ぶことで、カリッとした揚げ上がりが実現できます。また、揚げ物以外にも煮込み料理やスープ作りにも活用できるため、調理の幅が広がります。フタ付きのものを選べば、油はねを防ぐだけでなく、保温効果も期待できます。
パスタや炒め物に最適なフライパン
パスタや炒め物には24~26cmのフライパンが適しています。深めのデザインを選ぶと混ぜやすく、パスタソースが絡みやすいのが特徴です。また、底が広いフライパンを選ぶことで、均一に火が通り、炒めムラを防ぐことができます。さらに、食材をまとめて調理しやすいため、チャーハンや野菜炒めなどにも活用できます。素材としては、フッ素樹脂コーティングのものが焦げ付きにくく、鉄製のものは火力を強くすることで香ばしく仕上げることができます。
まとめ
フライパンのサイズを選ぶ際は、料理の種類や家族の人数を考慮することが重要です。また、素材によって使用感や手入れ方法が異なるため、自分のライフスタイルに合ったフライパンを選びましょう。